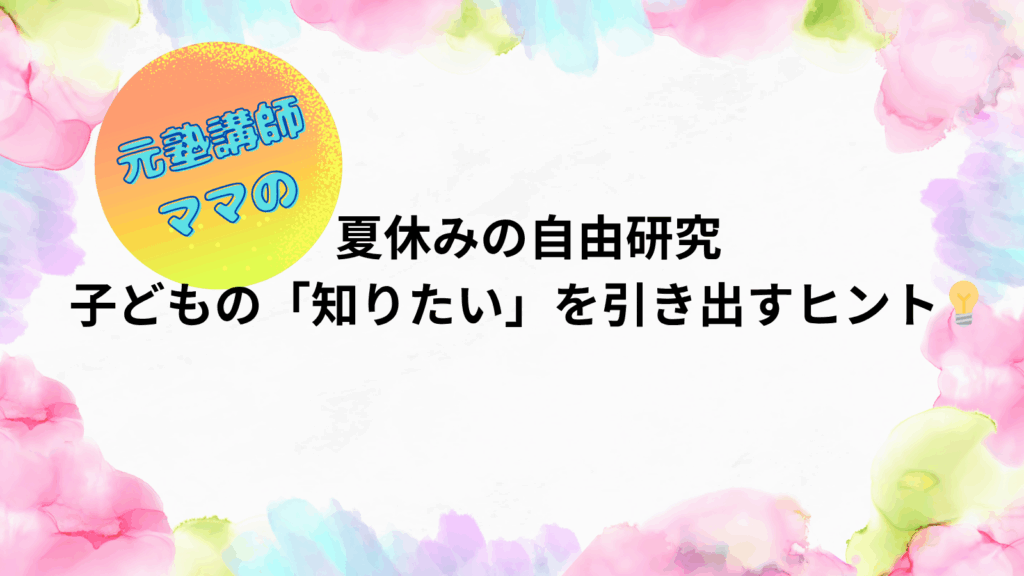
仕事に育児に、毎日奮闘中のワーママさん🎀
今日もお疲れさまです!✨
現役フルタイムで働きながら、
日々子育てに奮闘する二児のママ、わかママです。
これまで約10年以上、塾講師として
多くの子どもたちと向き合ってきました。
そんな私の自己紹介は、
こちらの記事で詳しくご紹介しています。
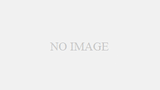
夏休みといえば、避けては通れないのが
自由研究ですよね😵💫
「テーマが決まらない!」
「どうやって進めればいいの…」
「結局親が手伝うことに…」
なんて声が聞こえてきそうです。
今回は、元塾講師の視点から、
夏休みの自由研究でうまく子どもの
「知りたい!」という探求心を
引き出すためのヒントをお伝えします😄
自由研究って、何のためにやるの?🤔
正直、「面倒だな…」と感じることもある
自由研究ですが、実は子どもにとって
大切な学びの機会なんです。
💪課題解決能力を育む:
疑問を見つけ、調べて、まとめるという
一連のプロセスは、社会に出てからも必要な
「課題解決能力」を養います。
💪探求心を刺激する:
自分の興味があることを深く掘り下げることで、
「もっと知りたい!」という
知的好奇心が育まれます。
😄表現力を磨く:
調べたことをどのように分かりやすく伝えるか、
試行錯誤することで表現力や
プレゼンテーション能力が向上します。
🌟【実践編】「知りたい」を引き出す3つのステップ✨
では、実際にどうすれば子どもが主体的に
自由研究に取り組めるようになるのでしょうか?🤔
塾講師時代に多くの子どもたちを
サポートしてきた経験から、
3つのステップをご紹介しますね。
ステップ1:テーマは「身近な疑問」から見つけよう🔍
「何の研究にしよう?」と最初から
壮大なテーマを探す必要はありません。
大切なのは、子ども自身が「なんでだろう?」
「これってどうなってるの?」と
素朴に感じる「身近な疑問」なんです。
「なんで朝顔って朝に咲くんだろう?」
「どうしてセミは木にとまっているんだろう?」
「お風呂の泡ってどうして消えるの?」
「スーパーの野菜、どこから来てるんだろう?」
虫好きなら「カブトムシの好きな餌は?」
料理好きなら「ジュースってどうやって作るの?」
ゲーム好きなら「キャラクターの動きの秘密は?」
親が誘導するのではなく、
子どもの「なんだろう?」というつぶやきを
大切に拾ってあげましょう。
ステップ2:調べる前に仮説を立てよう🤔
テーマが決まれば
早速答えを探しに行きたくなりますが、
その前に仮説を立ててみましょう。
「どうなると思う?」や
「どうなってると思う?」と問いかけて
子どもが考える仮説を引き出しましょう。
仮説があると自由研究の構成や
まとめがしやすくなりますよ😀
ステップ3:図書館や図鑑を「探検」しよう📚
テーマが決まり、仮説を立てたら、
次は情報収集です。
インターネットも便利ですが、
まずは図書館や図鑑を使って
「探検」する楽しさを教えてあげましょう。
まずは図鑑をパラパラ:
関連する図鑑や科学の本を一緒に見て、
気になるページがあれば
読み聞かせてあげましょう。
新しい発見があるかもしれません。
図書館へGO!: 専門の司書さんに
「〇〇について調べてるんですが…」
と相談すれば、子どもの興味に合った本を
たくさん紹介してくれます。
広い図書館で、宝探し気分で
関連図書を探すのも楽しいですよ。
実験のアイデアも豊富: 実験系の本には、
身近なものでできる簡単な実験が
たくさん載っています。
「これやってみたい!」
というものを見つけたら、
まずは真似してやってみましょう。
「自分で調べる」という体験が、
子どもの学びの幅を広げます。
忙しいワーママでもできる!無理なくサポートするヒント💡
「分かってはいるけど、時間がない…!」
そうですよね、私も毎日バタバタです。
でも大丈夫!
無理なくサポートするヒントがあります。
計画はざっくりでOK:
「この日にここまでやる」と細かく決めすぎず、
「今週はテーマを探そう」
「来週は図書館に行ってみよう」くらいの
ゆるい計画でOKです🗓️
声かけは「質問」中心で:
「何するの?」「いつやるの?」ではなく、
「ここはどうしてこうなるんだろう?」
「他に何か方法はないかな?」と、
子どもの思考を促す質問を投げかけてみましょう。
「失敗」も最高の学び:
実験がうまくいかなくても、
それが「なぜだろう?」という
次の探求に繋がります。
「失敗」という結果をそのまま
自由研究の報告とするのもアリですよ!
「来年再チャレンジする!」と
次の目標にするのも良いですね👍
夏休みの自由研究は、
親子のコミュニケーションを深める
絶好の機会でもあります。
完璧を目指さず、お子さんの
「知りたい!」を応援しながら、
一緒に夏休みの思い出を作ってくださいね🎌

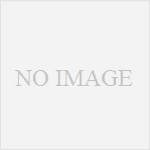
コメント